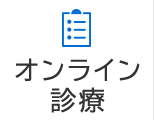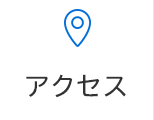更年期障害について
 症状としては、自律神経失調症状(のぼせ・ほてり・発汗・寒気・冷え症・動悸・胸痛・息苦しさ・疲れやすい・頭痛・肩こり・めまいなど)精神症状(イライラ・怒りっぽい・情緒不安定・抑うつ気分など)腰痛・関節痛・嘔気・食欲不振・皮膚の乾燥感やかゆみ・外陰部の不快感などさまざまな症状が起こります。しかし、これらの症状は更年期によるものとは限りません。
症状としては、自律神経失調症状(のぼせ・ほてり・発汗・寒気・冷え症・動悸・胸痛・息苦しさ・疲れやすい・頭痛・肩こり・めまいなど)精神症状(イライラ・怒りっぽい・情緒不安定・抑うつ気分など)腰痛・関節痛・嘔気・食欲不振・皮膚の乾燥感やかゆみ・外陰部の不快感などさまざまな症状が起こります。しかし、これらの症状は更年期によるものとは限りません。
更年期ではなく内科や外科の病気や精神科の病気がだったり、更年期と他の病気が同時に起こっていたりします。更年期障害ときめつけず、その症状に他の病気が隠れていないかを否定することがとても大切です。代表的な病気としては、甲状腺疾患などの内分泌疾患、循環器疾患や貧血、悪性腫瘍、うつ病などあげられますが、その病態はさまざまです。
当院では、更年期のご相談はまずは内科で診療します。理由としては、個人差はあるものの更年期は45歳~55歳前後の時期をいい、この時期はからだの変化、家庭、職場環境、精神的な要因などさまざまな要因による体調不良がでてきます。生活習慣病やそのほかさまざまな内科や自律神経の病気も見逃せません。このように更年期の期間の病気は多岐にわたるため、当院の更年期外来は、開業以来婦人科の診療に携わり、婦人科・内科の臨床経験豊富な総合内科専門医が行います。症状や検査結果により、婦人科による治療が必要と判断した場合は、婦人科専門医に引き継ぎますのでご安心ください。
更年期症候群の治療としては、漢方、プラセンタ療法、ホルモン補充療法などスタンダードな治療のほか、マイヤーズカクテル点滴栄養療法(自費)など、ビタミンやミネラルの点滴療法も行っています。ビタミンやミネラルを補充することで片頭痛や疲労(慢性疲労症候群を含む)、うつ状態などが改善するという報告があります。ご希望があれば、マイヤーズカクテル療法などの点滴療法(自費)も行っております。
体調不良を「更年期だから我慢すればいい」などと決めつけないでください。おひとりで悩まずに、まずは当院までご相談ください。
更年期障害の症状
主な症状
更年期障害の主な症状は、「ホットフラッシュ」と呼ばれるのぼせ、ほてり、発汗、動機などの血管運動系障害や、イライラ、怒りっぽい、不安、不眠、情緒不安定、抑うつ気分などの精神神経障害です。その他に、倦怠感や肩こり、めまい、腰痛、関節痛、頭痛、食欲不振、冷え性、皮膚粘膜の乾燥などさまざまな症状が現れることがあります。
このように更年期はさまざまな症状が生じるので、実は更年期ではなく内科の病気や精神科の病気がだったり、更年期と他の病気が同時に起こっていたりします。更年期障害ときめつけず、その症状に他の病気が隠れていないかを否定することがとても大切です。
男性の更年期障害
(LOH症候群/加齢性腺機能低下症)
男性にも加齢とともに、性ホルモンが低下したり、バランスが乱れることによって、様々な症状が現れることがあります(LOH症候群)。LOH症候群は「男性の更年期障害」と呼ばれることがあります。病気ではないのに漠然とした不調を抱えていたり、ほてりや発汗などの身体症状、やる気の低下やイライラなどの精神症状があり、生活に支障をきたしている場合は、男性の更年期障害の可能性があります。
更年期障害のセルフチェック
簡易更年期指数(SMIスコア)
更年期指数(SMIスコア)を採点することで、簡易的に自身が更年期障害であるかどうかを評価することができます。医療機関を受診する目安としてご活用ください。症状の程度に応じ、自分で○印をつけてから点数を入れ、その合計点をもとにチェックをします。
| 症状 | 強 | 中 | 弱 | 無 |
|---|---|---|---|---|
| 顔がほてる | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 汗をかきやすい | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 腰や手足が冷えやすい | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 息切れ、動機がする | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 寝つきが悪い、または眠りが浅い | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 怒りやすく、すぐイライラする | 12 | 8 | 4 | 0 |
| くよくよしたり、憂鬱になることがある | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 頭痛、めまい、吐き気がよくある | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 疲れやすい | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 肩こり、腰痛、手足の痛みがある | 7 | 5 | 3 | 0 |
更年期指数の自己採点の
評価法(合計点)
| 0~25点 | 上手に更年期を過ごしています。これまでの生活態度を続けてよいでしょう。 |
|---|---|
| 26~50 点 | 食事や運動に注意を払いましょう。無理をしないように生活しましょう。 |
| 51~65 点 | 医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。生活指導やカウンセリング、薬物療法などを行い、改善を目指します。 |
| 66~80 点 | 半年以上の計画的な治療が必要です。 |
| 81~100 点 |
医療機関を受診し、更年期障害なのか、その他の病気があるのか精査が必要です。更年期障害のみである場合は、長期的な治療が必要でしょう。 |
更年期障害の治療
ホルモン補充療法(HRT)
 ホルモン補充療法(HRT)とは、少量のエストロゲンを貼り薬や飲み薬、塗り薬によって補充する療法です。ホルモン補充療法は、更年期によるのぼせ、ほてり、発汗などの血管運動系障害を中心とした諸症状に効果があります。エストロゲン単体を補充すると、子宮内膜増殖症もリスクが上がるため、子宮がある方には併せてプロゲステロン(黄体ホルモン)を投与します。ホルモン補充療法に用いるホルモン剤には、飲み薬、貼り薬、塗り薬などいくつかの投与方法があるため、患者さんに合わせて最適な方法を選択していきます。ホルモン剤には血液を固まりやすくする働きがあるので、血栓症(血管の中に血液の塊ができて血管がつまりやすくなること)には注意が必要です。子宮がんや卵巣がん、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病や心臓、肝臓に病気のある方などはHRTを行ってよいか判断が必要です。
ホルモン補充療法(HRT)とは、少量のエストロゲンを貼り薬や飲み薬、塗り薬によって補充する療法です。ホルモン補充療法は、更年期によるのぼせ、ほてり、発汗などの血管運動系障害を中心とした諸症状に効果があります。エストロゲン単体を補充すると、子宮内膜増殖症もリスクが上がるため、子宮がある方には併せてプロゲステロン(黄体ホルモン)を投与します。ホルモン補充療法に用いるホルモン剤には、飲み薬、貼り薬、塗り薬などいくつかの投与方法があるため、患者さんに合わせて最適な方法を選択していきます。ホルモン剤には血液を固まりやすくする働きがあるので、血栓症(血管の中に血液の塊ができて血管がつまりやすくなること)には注意が必要です。子宮がんや卵巣がん、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病や心臓、肝臓に病気のある方などはHRTを行ってよいか判断が必要です。
当院では更年期治療については、まずは内科を受診していただきます。
開業以来産婦人科診療に携わり、臨床経験豊富な総合内科専門医が丁寧に症状を伺います。
まずはお悩みの症状が更年期かどうか必要な検査を行い、お悩みの症状に対して漢方治療やプラセンタ療法などを行います。
HRT療法が必要と判断した場合は日本産婦人科専門医に引き継ぎます。
2017年に「ホルモン補充療法のガイドライン」が出され、HRT療法を行ってはいけない場合が示されました。
- 重度の肝臓疾患の人
- 乳がんと乳がんの既往のある人
- 子宮内膜がんの人
- 原因不明の不正出血の人
- 妊娠が疑われる人
- 血栓性静脈炎、または静脈血栓塞栓症とその既往のある人
- 心筋梗塞、冠動脈に動脈硬化病変の既往のある人
- 脳卒中の既往のある人
その他肥満、60才以上、生活習慣病(高血圧、脂質異常、糖尿病など)、卵巣がん、子宮内膜がんの既往、血栓症リスクのある人、片頭痛、てんかん、肝疾患、胆石症の既往などの方は患者さんの症状とHRT療法を鑑み慎重な投与が必要です。
このようなことも踏まえて、当院の更年期治療の初期治療は内科で行っております。
漢方療法
 漢方療法とは、さまざまな生薬の組み合わせて作り出す漢方薬を用いた治療法です。
漢方療法とは、さまざまな生薬の組み合わせて作り出す漢方薬を用いた治療法です。
多彩な症状を訴える更年期女性に対しては、「婦人科三大処方」とも呼ばれる3つの漢方薬を中心に、さまざまな処方が用いられます。
| 漢方の種類 | 症状 |
| 桂枝茯苓丸 (けいしぶくりょうがん) |
体力中等度以上でのぼせ傾向にあり、下腹部に抵抗・圧痛を訴える方 |
|---|---|
| 加味逍遥散 (かみしょうようさん) |
比較的体質虚弱で疲労しやすく、不安・不眠などの精神症状を訴える方 |
| 当帰芍薬散 (とうきしゃくやくさん) |
比較的体力が低下しており、冷え症で貧血傾向がある方 |
このように更年期のさまざまな症状に漢方療法は適しており、一般的に副作用が少ないと考えられている漢方療法でも肝障害や、間質性肺炎、甘草含有処方(芍薬甘草湯や抑肝散など)による偽性アルドステロン症すなわち、高血圧、低カリウム血症、横紋筋融解症、不整脈、サンシン含有製剤(加味逍遙散、防風通聖散など)は長期間の内服で大腸の色素異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症」が現れる可能性が報告されています。特に漢方薬の併用は生薬の過剰投与になる可能性があるので、処方には注意が必要です。最近では一般医薬品(OTC医薬品)にも漢方成分が多くあり、複数の医療機関で漢方を処方されている場合は注意が必要です。
プラセンタ療法
 プラセンタ療法とは、ヒトの胎盤から抽出した栄養成分(プラセンタエキス)を、注射や内服によって体内に取り込む治療法です。胎盤には、タンパク質や脂質、糖質のほかに、アミノ酸やビタミン、酵素、核酸などの体の生成に必要な豊富な栄養素が含まれており、これらの栄養素によって細胞が活性化します。また、プラセンタエキスには新陳代謝が活発化され、体内の状態を本来の状態に戻そうとする効果があります。
プラセンタ療法とは、ヒトの胎盤から抽出した栄養成分(プラセンタエキス)を、注射や内服によって体内に取り込む治療法です。胎盤には、タンパク質や脂質、糖質のほかに、アミノ酸やビタミン、酵素、核酸などの体の生成に必要な豊富な栄養素が含まれており、これらの栄養素によって細胞が活性化します。また、プラセンタエキスには新陳代謝が活発化され、体内の状態を本来の状態に戻そうとする効果があります。
プラセンタ注射の効果持続期間は2,3日と言われています。初回投与から、だいたい2~3回の治療で効果を実感できる方が多いです。「疲れにくくなった」「よく眠れる」「肌に張りがでてきた」などと言われる方が多いです。最初のうちはできれば週2回、効果が実感できてきたら週1回に減らしてもよいでしょう。
プラセンタの種類
プラセンタ注射
現在、厚生労働省から認可されているプラセンタ製剤は、「ラエンネック」と「メルスモン」の2種類があります。更年期障害に保険適応されているのはメルスモンだけです。当院では、保険診療の他に、自費診療として、アンチエイジングや美肌効果、血行促進、抗アレルギー・抗炎症効果を目的としたプラセンタ注射も行っています。
内服用プラセンタ
当院では、忙しくてなかなか通院できない方や注射が苦手な方のためにプラセンタの内服薬もご用意しています。もちろんプラセンタ注射と併用することで治療効果が持続できます。プラセンタの内服はブタ由来のプラセンタ(胎盤)エキス100%です。添加物を一切含まない純粋なプラセンタエキスです。1日3~6粒の内服が目安です。注射1回分は約6カプセルです。
以下の方は飲み薬のプラセンタがおすすめです。
- 忙しくてなかなか受診できない
- 注射が苦手
- 毎日プラセンタを飲みたい
- 長期の出張や旅行の時にもプラセンタを飲みたい
プラセンタの有効作用
- 活性酸素除去作用(活性酸素を除去することで老化防止、アンチエイジング)
- 美肌促進作用(美白効果、シミ・しわ・ニキビ・肌荒れ、乾燥肌予防)
- 抗アレルギー作用、花粉症
- 免疫賦活(ふかつ)作用:抵抗力・免疫力を向上
- 強肝・解毒作用(肝臓機能を向上)
- 疲労回復作用
- 肩こり、自律神経失調症、冷え性、不眠症
プラセンタの副作用
医薬品ですのでまれにアレルギー症状が出る方がいます。この場合は、残念ながら継続治療ができません。そのほか更年期治療のプラセンタ(メルスモン)は、皮下注射なので注射部位の痛みや皮下出血、硬結などがあります。自費治療のプラセンタ(ラエンネック)も同様です。当院では、週2回以上接種する方は左右で部位を変更するなどの対応をしています。
料金
保険適用の場合
更年期障害に対するプラセンタ療法の保険適用対象は、更年期障害と診断された45~59歳の女性になります。当院では、問診で更年期指数(SMIスコア)を確認し、婦人科と内科の臨床経験豊富な総合内科専門医が問診、診察、採血など必要な検査を行います。プラセンタの効果、副作用、治療方法をご説明してから治療開始となります。プラセンタ療法の効果の現れ方は、個人差があり、体調や環境などによっても異なるため、経過を観察しながら、注射の頻度を決めていきます。一般的には、週2~3回の頻度で、継続してくのが最も効果が出やすいとされています。定期的に治療効果、副作用の確認をして、治療方法をご相談しています。
| 3割負担 | |
| 初回 | 約1,000円 |
|---|---|
| 2回目 | 約530~560円 |
保険適応外(自費)の場合:【プラセンタ(ラエンネック)】
 男女、年齢制限なく、どなたでもプラセンタ療法を受けていただくことができます。(まれにアレルギーや体質に合わない方もいます)成長因子と呼ばれている成分は細胞の動きを活発化させ、更年期障害だけではなく、様々な症状の改善薬として使用されています。アンチエイジング、健康維持、疲労回復、生理不順、生理痛、美白、くすみ、たるみ、肌のきめ、小じわの解消、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、気管支喘息、リウマチなど
男女、年齢制限なく、どなたでもプラセンタ療法を受けていただくことができます。(まれにアレルギーや体質に合わない方もいます)成長因子と呼ばれている成分は細胞の動きを活発化させ、更年期障害だけではなく、様々な症状の改善薬として使用されています。アンチエイジング、健康維持、疲労回復、生理不順、生理痛、美白、くすみ、たるみ、肌のきめ、小じわの解消、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、気管支喘息、リウマチなど
| 料金(税込) | |
| プラセンタ注射1本 | 1,700円 |
|---|---|
| プラセンタ注射2本 | 2,500円 |
| プラセンタ注射3本 | 3,000円 |
|
内服用プラセンタ |
17,000円 |
| 内服用プラセンタ ラエンネックP.Oポーサイン(お試し用 20カプセル) |
3,700円 |
当院では、プラセンタに各種ビタミン剤を配合しています。
別途初回診察料(自費) 3,300円(税込)かかります。
2回目から診察料(自費)1,100円(税込)かかります。(前回接種から3か月以内であれば再診料なし)
注意点
プラセンタエキスはヒトの胎盤を原料としており、理論上未知のウイルスなどによる感染症にかかる可能性を完全には否定できません。しかし、B型肝炎、C型肝炎、HIVなどの各種ウイルスのチェックや酵素処理、高圧滅菌によりウイルスを不活化されています。日本では昭和31年からプラセンタ注射が開始されましたが、これまでにクロイツフェルト・ヤコブ病も含めて感染症の報告はありません。
しかし厚生省の判断で、理論上感染の危険性がゼロでないので献血はできないと定められています。ですから、プラセンタ製剤を投与した場合は献血ができなくなりますのでご注意ください。
ビタミン点滴療法(自費)
更年期症候群の治療としては、漢方、プラセンタ療法、ホルモン補充療法などスタンダードな治療のほか、高濃度ビタミンC療法(25g),マイヤーズカクテル点滴栄養療法(自費)など、ビタミンやミネラルの点滴療法も行っています。ビタミンやミネラルを補充することで片頭痛や疲労(慢性疲労症候群を含む)、ストレスによる体調不良、うつ状態などが改善するという報告があります。プラセンタ療法(ラエンネック自費)と併用することで効果はさらに期待できます。
向精神薬
(抗うつ薬や抗不安薬)
更年期障害で、気分の落ち込みや意欲の低下、イライラ、情緒不安定、不眠などの精神症状が最もつらい症状である場合は、抗うつ薬や抗不安薬、催眠鎮静剤などの向精神薬などを用います。SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬は、副作用が少なく、ほてりや発汗などの血管運動系障害にも効果があることが知られています。
心療内科での治療が望ましいと判断した場合は、ご紹介させていただきます。
更年期に気を付けたい疾患
更年期は、更年期障害以外にも様々な病気を発症するリスクが高い時期です。特に、女性の身体は閉経後、大幅に病気にかかるリスクが上がります。更年期症状を改善するだけでなく、他の病気にも気をつけながら、先回りしてケアを行いましょう。
高血圧・脂質異常症
女性ホルモンは、全身の血管をしなやかに保つ役割と、内臓脂肪を分解する役割があります。そのため、女性は閉経すると、高血圧や脂質異常症の発症・進行リスクが高まります。高血圧や脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、動脈硬化を促し、脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な病気の引き金になるため、健康診断などを定期的に受けるようにしましょう。
骨粗しょう症
女性ホルモンは、骨の代謝を正常に保つ働きがあります。そのため、女性は閉経すると、骨代謝のバランスが崩れ、骨粗しょう症の発症リスクが高まります。骨粗しょう症とは、骨の強度が低下して、骨が折れやすくなる病気です。骨粗しょう症を発症すると、転んだだけで骨折したり、寝たきりになってしまいます。また、さらに症状が悪化すると、体の重みだけで背骨が潰れてしまったり、背骨が曲がってしまいます。骨粗しょう症の予防には、食事や運動によって骨の強度を維持することや、骨密度測定などの検査を定期的に受けることが効果的です。
大田区では45才以上の女性は5年毎に大田区内に住民票のある40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性「骨粗しょう症検診」が受けられます。当院でも受けていただけます。
その他
閉経によって老化現象が加速することがあります。加齢によってドライアイやドライマウスを発症しやすくなり、また膣も乾燥しやすくなるため、感染リスクが高まります。特にドライマウスは誤嚥を起こしやすくするため、予防が重要です。さらに消化器官の蠕動運動も低下するため、下痢や便秘が起こりやすくなります。骨盤底筋が弱くなると、尿漏れや過活動膀胱が起こります。分娩経験がある方は子宮脱を起こす恐れもあります。