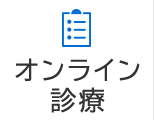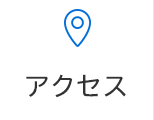高血圧

高血圧とは、血圧が高い状態です。たまたま測った血圧が高いのではなく、くり返しの測定で、最高血圧140mmHg以上もしくは最低血圧90mmHg以上の状態のことを言います。最高血圧とは、心臓が収縮する際にかかる血管への圧力のことで、最低血圧とは、心臓が収縮後元の大きさに戻るときにかかっている血管の圧力のことです。最高血圧、最低血圧のどちらが基準値を超えていても高血圧と診断されます。
高血圧は放置しておくと、心不全や狭心症、心筋梗塞、脳出血、脳梗塞といった心臓や脳の血管の病気につながるため、食事療法や運動療法によって治療していく必要があります。
高血圧の症状
高血圧は、ほとんどの場合で自覚症状がありません。しかし、高血圧を放置していると、強い圧力によって血管が傷つき、血管が厚く硬く変化していく「動脈硬化」が起こります。また、動脈硬化はさらに高血圧を促進するため、その特徴から、高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれることがあります。当院では超音波技師による頸動脈エコーを行っています。
高血圧が引き起こす
主な病気
脳血管障害
脳血管障害とは、脳出血や脳梗塞などの脳血管に異常が起こる病気の総称です。高血圧に加えて、糖尿病や脂質異常症などの病気を合併している場合に、脳血管障害の発症リスクが高くなることが知られています。
心臓病
心臓病とは、心臓の異常によって生じる病気の総称です。高血圧によって心臓に負荷がかかると、心臓の壁が分厚くなる「心肥大」や心臓ポンプ機能が低下する「心不全」が起こりやすくなります。また、心臓自体に酸素や栄養を送る「冠状動脈」に動脈硬化が起こると、心筋梗塞や狭心症を発症しやすくなります。
高血圧性網膜症
高血圧性網膜症とは、高血圧が原因となり、眼底の血管が詰まったり、出血したりすることで網膜に機能障害が起こる病気です。視力障害などの症状が現れます。
高血圧性腎硬化症・腎不全
高血圧性腎硬化症とは、高血圧によって腎臓の血管に動脈硬化が起こることで、腎臓にある血液をろ過して老廃物を除去する「糸球体」への血流が乏しくなり、腎機能が低下する病気です。高血圧性腎硬化症がさらに悪化すると、慢性腎不全に至ることがあります。
女性の高血圧
女性は更年期(閉経前後)になると、エストロゲンが急激に減少すること自体や、エストロゲンの減少によって自律神経が乱れ血圧が不安定になることによって高血圧になることがあります。さらに更年期は子どもの独立や親の介護などの環境の変化が重なることが多いため、不安やストレスを抱えやすく、高血圧になることがあります。
当院では、開業以来婦人科診療に携わってきた臨床経験豊富な総合内科専門医が診療しています。更年期の高血圧(閉経後高血圧)や原発性高血圧など血圧が高いと気になったときは悩まずにご相談ください。
高血圧の治療
高血圧の治療では、食事療法と運動療法が基本となります。また、必要に応じて、薬物療法を行うこともあります。
食事療法
食事療法では、塩分やアルコールの摂取量を減らし、野菜や果物を多めに摂るバランスの取れた食事を取る食生活に変更していきます。外食や居酒屋などでの食事は、味が濃いことが多いため、外食を控え、和食中心の塩分控えめな自炊の割合を増やすことが効果的です。また、できる限り禁煙してください。
運動療法
運動療法では、ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を中心とした、適度な運動習慣を生活に取り入れていく治療です。年齢や身体の状態に合わせて無理なく続けられる範囲で行っていきましょう。通勤時に1駅分歩くようにしたり、エレベータではなく階段を使うようにするといった方法も有効です。
薬物療法
薬物療法では、主に降圧剤を処方します。降圧剤は、血圧を下げる薬ですが、心臓が送り出す血液量を減らすことで血圧を下げるものや、尿量を増やして血液量を減らすことで血圧を下げるもの、自律神経に作用して血管の収縮を抑制することで血圧を下げるもの、血圧の上昇を招く物質を減らすことで血圧を下げるものなど、様々な種類があります。降圧剤は患者さんの状態に合わせて選択し、処方いたします。
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症とは
下記状態のことであり、平成19(2007)年に名称が改められ、「高脂血症」から「脂質異常症」と呼ばれるようになりました。
- 中性脂肪が150mg/dL以上(空腹時)もしくは175mg/dL以上(随時)
- LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が140mg/dL以上
- Non-HDLコレステロールが170mg/dL以上
- HDLコレステロール(善玉コレステロール)が40mg/dL未満
脂質異常症の症状
脂質異常症は自覚症状がないことが多いため、健康診断で発覚することがほとんどです。脂質異常症は放置すると、血管の内壁に脂質が蓄積し、血流を阻害し、動脈硬化を引き起こします。脂質異常症は早めに治療を行えば、脳血管障害や心筋梗塞などの重大な病気を防ぐことができますが、自覚症状がないため、気づいたときには既にかなり進行してしまっていることが多いです。
女性の脂質異常症
血液中のコレステロールは、女性ホルモンのエストロゲンの働きによって調整されるため、更年期の女性は、エストロゲンの減少によって血液中のコレステロールが上昇しやすくなります。そのため、生活習慣が乱れているわけでなくても、脂質異常症が起こりやすいです。
痩せている人も要注意
脂質異常症は脂質という言葉が付いているため、太っている人がなる病気と思われがちですが、実際には普通体系や痩せ型であっても脂質異常症のリスクが高い方もいます。これは、現代の食事に含まれる飽和脂肪酸の量が増加していることが背景にあるとされています。特に血縁者に脂質異常症患者がいる方や、ダイエットで糖質を控える代わりに動物性脂肪を多く摂っている方は要注意です。また、脂質異常症のリスクとなる内臓脂肪は、皮下脂肪と比べて外見ではわかりにくい傾向があるため、普通体系や痩せ型だからと言って、脂質異常症とは無関係なわけではありません。健康診断などで脂質異常を指摘された方は必要に応じて検査や治療を受けましょう。
脂質異常症の治療
脂質異常症の治療では、食事療法と運動療法を中心に行い、効果が十分現れない場合には、薬物療法を取り入れます。また、状態によっては、食事療法・運動療法と薬物療法を同時に開始することもあります。
食事療法
食事療法では、カロリーコントロールを中心に、栄養バランスの取れた食事を取っていきます。また肥満の方の場合は、肥満の解消を目指します。
調理のポイント
脂質異常症に対する食事療法では、どんな食材を食べるかのほかに、「どのような調理方法で調理するか」も重要になります。コレステロールの摂取量を抑えるためには、焼く、揚げるなどの調理法を避け、「蒸す」、「煮る」などの調理法を選択するのがおすすめです。また、「食材は大きめにカットする」と、自然とよく噛むようになり、満腹中枢が刺激されやすく、食べ過ぎを予防することができます。また、「出汁」や「香辛料」を効果的に使い、塩分を減らすようにしましょう。
運動療法

運動療法では、ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を、1日30分程度、1週間で180分以上行います。数字だけ見ると、大変そうに見えますが、通勤や買い物での行き帰りで歩いた時間なども含めることができるため、継続可能な範囲で行っていきましょう。通勤時に1駅分歩くようにしたり、毎日スーパーに買い物に歩いて行くようにするなど、ちょっとした工夫を取り入れることで、継続しやすくなります。
薬物療法
薬物療法では、血液中の中性脂肪やLDLコレステロールの量を減らす薬を使用します。薬物療法を取り入れても、食事療法や運動療法は継続するようにしてください。
禁煙
たばこに含まれるニコチンには、中性脂肪の原料となる遊離脂肪酸を増加させる作用や、LDLコレステロールの酸化を進行させる作用、HDLコレステロールの濃度を減少させる作用があり、食事療法や運動療法、食事療法の効果を阻害する要因になります。脂質異常症の治療をしている方は、禁煙するようにしましょう。