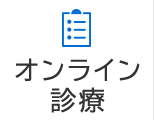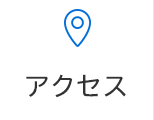発熱外来とは
 発熱外来とは、発熱を伴う風邪のような症状の検査や治療を行う診療科です。
発熱外来とは、発熱を伴う風邪のような症状の検査や治療を行う診療科です。
発熱外来では、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症の感染拡大を防ぐために、発熱のある患者さんをわけて診療を行います。
発熱外来を受診する目安
日本の感染症法では、体温が37.5℃以上の状態を「発熱」、38℃以上の状態を「高熱」と定義しています。しかし、37.5℃に達していなくても、平熱より1℃以上体温が高い状態が続いている場合や、発熱に伴い喉の痛みや咳、鼻水、痰、倦怠感、息苦しさなどの症状がある場合、感染症の重症化のリスクが高いと考えられる場合には、医療機関を受診しましょう。
発熱外来の流れ
1必ず来院の前にお電話
(03-3731-2122)
にてご相談ください
- どんな症状があるか?(体温、咳、喉の痛み、鼻水、関節痛など)
- いつから症状があるか?
- インフルエンザ、新型コロナウイルスの感染者と接触したか?
2ご来院時間をご相談させて
いただきます。
3医師が必要と判断し、ご本人も検査をご希望される場合に、検査を行います。
検査結果は受診時にお伝えします。症状と検査結果に基づいて治療を行います。
当院で可能な検査・料金
(保険診療3割負担)
| 検査の種類 | 結果が出るまで | 料金 |
|---|---|---|
|
抗原検査 (インフルエンザ・新型コロナウイルス) |
即日検査 (5~15分程度) |
約2,400円 |
|
PCR検査 (新型コロナウイルス) |
即日検査 |
約3,800円 |
大人が発熱したときの対処法
風邪の引き始め
 風邪の引き始めは、「体を温めること」が重要です。
風邪の引き始めは、「体を温めること」が重要です。
体を温めるには、以下の方法が有効です。
部屋を暖かくする
暖房器具を利用して、部屋全体を温めたり、温かい部屋に移動して過ごしましょう。
適切な衣服を着る
温かい素材の衣服を着たり、重ね着をすることで体を温めましょう。頭や首元、手足も帽子やマフラー、手袋や靴下などを着用することで温めることができます。
布団に入る
寝る際は、布団に入り体を温めましょう。必要に応じて、毛布や電気毛布などを使うのも良いでしょう。
温かい食材・飲み物を摂る
温かいスープやハーブティー、ジンジャーティーなどを飲んで、体を中から温めましょう。
熱が上がりきって汗を
かきはじめたら
体内のウイルスが減少すると、体温調整中枢の体温設定が低く変更され、体は発汗して、体温を下げ始めます。この段階では、暑さを感じ、汗をかき、顔が火照ります。発汗が始まったら、汗を清潔なお洋服に着替え、体を冷やさないようにしましょう。タオルで包んだ保冷剤などを脇の下や首筋、脚の付け根に当てることも体温を下げるのに有効です。
大人がインフルエンザ・
新型コロナウイルス感染症と
診断されたら
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症と診断されたら、発症後3~7日は、鼻や喉からウイルスが排出されるため、この期間は外出を控える必要があります。また、排出されるウイルスの量は、解熱に伴って減少していくとされていますが、解熱後はウイルスを排出しないということではないため、解熱後も周囲に感染を広げる可能性はあります。ウイルスの排出期間の長さには個人差がありますが、解熱後も咳やくしゃみなどの症状が続いている場合には、なるべく外出を控え、マスクを着用するなど、周囲の人へ感染を広げないように配慮しましょう。なお、学生は学校保健安全法では、発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまでの期間を出席停止期間と定めています。これは学校保健安全法なので大人の場合は職場との相談になります。
インフルエンザの治療
発症から48時間以内であればインフルエンザウイルスの増殖を抑制する薬があります。インフルエンザA、B型に共通な抗インフルエンザウイルス薬が、A型のみに効果のある抗インフルエンザ薬があり、いずれも保険が適応されています。小児用のドライシロップもあります。インフルエンザウイルスは体内で急激に増殖するため、なるべく早めに内服することが大切です。早期であれば、ウイルス量も少ないので治療効果が高いです。
妊娠中の場合
インフルエンザ発症から48時間以内に抗インフルエンザウイルス薬を内服すると発熱期間が1、2日短縮され、ウイルス排出量も減り、重症化を抑制できます。米国疾病予防局(CDC)は、妊娠中と分娩後2週間以内は、抗インフルエンザウイルス薬の治療を推奨しています。婦さんへの投与による胎児の有害事象は報告されていません。ラピアクタ、ゾルフーザは添付文書上有益性投与となっているが、今のところ妊婦に対する有効性や安全性に関するデータはありません。
インフルエンザ患者と濃厚接触した場合のタミフルやリレンザの予防投与(自費)を広く行うことは、薬剤性抵抗インフルエンザウイルスの出現が懸念されガイドラインでも推奨されていません。しかし、インフルエンザ発症で重症化しやすい妊娠中や分娩後2週間以内の褥婦に対しては予防投与(自費)も考慮されています。(産婦人科ガイドライン2023より)当院の内科までご相談ください。
授乳中の場合
母乳を介して赤ちゃんにインフルエンザウイルスが感染することはありません。しかし、お母さんの咳やくしゃみ、手や服についたウイルスから感染することがあります。
授乳について
- 抗インフルエンザウイルス薬を2日以上内服している
- 解熱している
- 咳、鼻水がない
の3つの条件をクリアしてからの授乳が勧められています。
条件を満たさない場合は、搾乳して、インフルエンザ症状のない方が赤ちゃんにあげてください。
抗インフルエンザウイルス薬の服用について
タミフルやリレンザなどの抗インフルエンザウイルス薬を内服すると、極微量の薬剤が母乳に含まれます。添付文書には「授乳婦に投与する場合は授乳を避けること」と記載されています。欧米では母乳への以降は極微量なので授乳の継続は可能とされています。
新型コロナウイルス感染症の治療
症状が軽い人は、症状によって解熱剤や咳止めなど対症療法で対応します。ただし、症状が軽くても重症化するリスクのある人がいます。
高齢者、持病がある(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)、免疫不全を起こす薬を内服されている方、肥満、妊婦さんです。
持病がある方が発熱したら医療機関への受診をおすすめします。
感染症の予防
予防接種
ウイルス感染症の中にはインフルエンザのように予防接種が有効なウイルスもあります。インフルエンザから身を守るために最も有効な方法は、流行前に予防接種を受けることです。予防接種を受けることで、インフルエンザにかかりにくくなります。また、もしインフルエンザにかかったとしても重い症状になることを防ぐことができます。但し、インフルエンザワクチン接種後、免疫力がつくまでに2週間程度かかりますのでご注意ください。ワクチンの効果が持続するのは約5ヶ月間と言われています。
手洗い
ウイルスは、公共の場所のドアノブやつり革、手すり、照明やエレベーターのボタン、トイレのボタンなどに付着しやすいです。家に帰った後や料理をする前、食べたり飲んだりする前後はきちんと手を洗うようにしましょう。アルコール消毒も有効です。
※ノロウイルスはアルコール除菌が効きにくいのでご注意ください。
適度な湿度を保つ
ウイルスは、寒さと乾燥を好むので、空気が乾燥しているとウイルスが長時間空気中を漂ってしまいます。空気が乾燥すると、気道にウイルスがくっつきやすくなります。室内を加湿器などで適度な湿度(50-60%)に保ちましょう。
マスクの着用
ウイルスは、感染者の咳やくしゃみによって飛び散ります。
マスクの着用は感染予防の効果よりも、自分が感染しているときに他人に移さない効果の方が大きいとされていますが、感染防止にも一定の効果があります。
感染症の流行時期には、人が多い場所ではマスクを着用することがおすすめです。また、マスクの着用は、喉の乾燥を防ぐ効果もあるため、感染予防につながります。
十分な休養と栄養バランス
睡眠不足や、偏った食事をしていると抵抗力が低下しウイルスにかかりやすくなります。十分な休養とバランスのとれた食事を摂るようにしましょう。