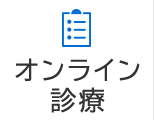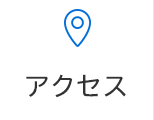糖尿病

糖尿病とは、何らかの原因でインスリンの働きが低下したり、量が不足することで、血液中のブドウ糖の量が多くなっている状態です。また、糖尿病は特に自覚症状が無くても、合併症を引き起こすリスクがあり、放置すると、様々な全身症状を引き起こすため、適切な治療を受けることが重要です。健康診断などで、血糖値が高いとわかった方や、糖尿病と診断を受けたものの治療を開始していない方は、一度当院までご相談ください。
毎週水曜日14:30~17:30(17時受付終了)は東邦大学内分泌センターの医師による診療日です。
インスリンとは
インスリンとは膵臓から分泌され、血糖を下げる唯一のホルモンで、食後に血糖値が上がらないよう調節をする働きをします。また、血液中のブドウ糖をからだの細胞に送り込んで、活動エネルギーに変えたり、脂肪やグリコーゲンに変えてエネルギーを蓄えたりします。
糖尿病の種類
1型糖尿病
1型糖尿病とは、膵臓のインスリンを出す細胞(β細胞)が壊されてしまう病気です。原因は不明な点もありますが、約90%が自己免疫性、残り10%が特発性(原因不明)とされています。甲状腺疾患を併発することもあります。またウイルス感染などが原因と示唆する報告も多くみられます。通常遺伝はしません。しかし特定の遺伝子を有する患者さんでは家庭内での発症もみられます。糖尿病の症状をコントロールするためには、原則的にインスリン療法が不可欠になります。インスリン治療に加えて『糖の吸収・排泄を調整する薬(αーグルコシダーゼ阻害薬、SGLT2阻害薬の一部』を患者さんの症状にあわせて投与することもあります。
2型糖尿病
2型糖尿病とは、遺伝的素因によるインスリン分泌能の低下に生活習慣の乱れが原因となり、インスリンの働きに異常が起こることで血糖値が下がらなくなる糖尿病です。日本の糖尿病患者の大半は、2型糖尿病であるとされています。必ずしもインスリン療法による治療が必要であるとは限らないことから、「インスリン非依存性糖尿病」とも呼ばれています。2型糖尿病ではインスリンによる血糖低下作用が低下していることと、膵β細胞からのインスリン分泌が不十分なこと、その両方の異常があり血糖値が上がります。2型糖尿病は1型糖尿病よりもゆっくりと気づかないうちに発症しゆっくりと進行する場合が多いです。
妊娠糖尿病
妊娠糖尿病とは、妊娠期に胎盤が作るホルモンによって、インスリンの働きが抑えられ、血糖が上昇する糖代謝異常のことを言います。妊娠中は、わずかな高血糖でも胎児に影響を及ぼすため、糖尿病には至っていない場合でも、「妊娠糖尿病」と呼びます。肥満の方や高齢妊娠の方、家族に2型糖尿病患者がいる方、過去の妊娠で高血糖を指摘された方などに起こりやすいとされています。当院では妊娠初期に血糖値を測定し、妊娠糖尿病のスクリーニング検査を行っています。
その他
その他の糖尿病として、遺伝子の異常や他の病気、薬剤に伴って起こるものがあります。
糖尿病の代表的な症状
糖尿病の代表的な症状は以下の通りです。
糖尿病が軽症である場合は、自覚症状がないことが多いため、発見が遅れやすいです。
尿の量が多くなる(多尿)
糖が尿に出るときに同時に水分も一緒に尿に出るため、尿の量が多くなります。
のどが渇いて、水分をたくさん飲む(口渇、多飲)
尿の量が多くなることで脱水状態となり、のどが渇き、水分をたくさん摂りたくなります。
体重が減る
糖が尿に出るために、たんぱく質や脂肪を利用しエネルギーを生み出すため、体重が減少します。
疲れやすくなる
エネルギー不足と、体重減少により疲れを感じやすくなります。
糖尿病の合併症
血糖値が高い状態が長く続くと、体内の細い血管が障害され、血流が悪くなり、特に細い血管が集中しているような、目や手足の末端などに合併症が起こります。
細小血管障害
網膜症
目の網膜に障害が起こり、視力低下を起こし、最終的には失明に至ります。
腎症
腎臓に障害が起こることで、腎臓の働きが低下し体内に老廃物がたまります。進行すると、透析や腎移植が必要になります。
神経障害
神経に障害が起こり、手足のしびれや痛み、感覚低下が起こります。
大血管障害
血糖値が高い状態が長く続くと、動脈硬化が進行します。動脈硬化は、脳梗塞や心筋梗塞、末梢動脈疾患(PAD)などを引き起こします。
その他
高血糖は、血管の障害以外に、歯周病を引き起こしたり、肺結核や尿路感染症、皮膚感染症などの感染症にかかりやすくします。また、足に起こる皮膚感染症は、壊疽(えそ)を招くことがあります。
糖尿病の治療

治療の基本は、食事療法や運動療法といった生活習慣の改善です。食事療法では、食事内容に加え、食べる順番やタイミングも重要なポイントとなります。運動療法では、日常生活に取り入れやすく、無理なく続けられる運動メニューの指導をします。これらの生活習慣の改善だけで十分な効果が得られない場合には、薬物療法を併用し、血糖値を適切にコントロールします。
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センターの医師の診療日
糖尿病でお困りの方はお気軽にご相談ください。
毎週水曜日:14:30~17:30(最終受付17:00)
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センターの医師の診療日です。
甲状腺疾患
甲状腺疾患は日本人女性がなりやすい
疾患の1つです。
「橋本病」に代表される機能低下症、
「バセドウ病」に代表される機能亢進症、
甲状腺がんなどの腫瘍性疾患などの総称です。
甲状腺とは
甲状腺とは、のどぼとけの下にある、蝶が羽を広げたような形をしたホルモン分泌器官であり、縦2~3cm、横4~5cm、厚さ1cm程度の小さな臓器です。甲状腺は、海藻などに含まれるヨードという栄養素をもとに、甲状腺ホルモンという全身の新陳代謝を活性化するホルモンを産生し分泌しています。甲状腺ホルモンは多すぎると新陳代謝が活発になり過ぎて興奮状態が続いてしまい、逆に少なすぎると気力や活力が低下してしまうため、適切な分泌量が必要です。
甲状腺疾患の初期症状
甲状腺の病気で甲状腺が腫れないケースはめったにないと言われるほど、ご来院のきっかけとして最も多いのは首の腫れです。甲状腺が腫れると首の前部が目立つので、鏡を見てご自身で気付いたり、周りの方や検診で指摘される場合があります。また、イライラやうつ症状、認知症などの精神的な症状がきっかけで診断される方もあります。更年期症状かと思ったら甲状腺疾患だったというケースも少なくありません。
医療機関受診の目安
甲状腺の病気は自覚症状が少ないものが多く、異常に気付くことが難しいという特徴があるため、気づいたときには、症状が進行してしまっているということもあります。首の腫れやしこりがある場合には、できるだけ早く医療機関を受診してください。
当院では超音波検査技師による甲状腺エコーを行っています。病状や進行状態によっては、より精密な検査や治療が必要になることがあるため、必要と判断した場合には、提携の専門医療機関をご紹介します。
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センターの医師の診療日
毎週水曜日:14:30~17:30(最終受付17:00)
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センターの医師の診療日です。
お気軽にご相談ください。