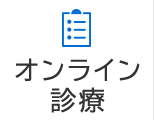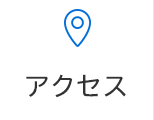皮膚科について
皮膚科とは、皮膚や爪などの病気を診察・治療する診療科です。当院では、湿疹、蕁麻疹(じんましん)、ニキビ、水虫、アトピー性皮膚炎、虫さされ、円形脱毛症、帯状疱疹、単純ヘルペス、などの様々な皮膚症状の診察を行っています。治療は、基本的には保険診療内で行っていますが、ニキビやニキビ痕、シミ、などについては保険外診療の施術も行っています。(ケミカルピーリングやビタミン注射、美白注射、白玉点滴、高濃度ビタミンC点滴療法など)
にきびやシミの症状を拝見し、オリジナルの治療計画をたてますので、まずはご相談ください。
当院で診療している
症状、病気・お悩み
-
- 皮膚のかゆみ
- 皮膚が赤くなる・紫になる
- 湿疹・皮膚炎
(アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、あせも など) - ニキビ(ニキビ治療)
- じんましん(コリン性じんましん、寒冷じんましん)
- 乾癬(診断が確定している方の継続治療)
- 多汗症(外用薬治療のみ)
-
円形脱毛症
- 粉瘤(外科的処置は行っておりません)
- ウイルス感染
ヘルペス、帯状疱疹 - 細菌感染症(とびひ、毛包炎)
- 真菌症
白癬(水虫、爪水虫)、カンジダ症、癜風(くろなまず) - シミ・くすみ(シミ・くすみ治療)
など
※切開などの外科的処置は行っておりません。外科的処置が必要と判断した場合は対応可能な医療機関をご紹介させていただきます。
よくある症状
かゆみ

かゆみは、アレルギー反応や乾燥、虫刺され、皮膚疾患などで起こる症状です。何度も掻きつづけると、傷ついた皮膚から細菌が入り込み、化膿したり、感染症を起こしたり、することがあります。また、かゆみが続いたり、全身にひろがる場合は、肝臓や腎臓など内臓の病気が隠れている可能性もあります。原因を特定し、適切な治療をすることが大切です。
湿疹
湿疹は、皮膚に赤みやブツブツ、小さな水疱などが現れる症状で、かゆみを伴うことが多いです。原因は、病原体(細菌や真菌)、薬剤、化学物質、アレルギー物質(金属や花粉)、日光、汗の刺激などさまざまです。複数の要因が関与している場合や原因がわからない場合もあります。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、赤みやかゆみを伴う湿疹がくりかえし現れる疾患です。原因は、遺伝(体質)やダニやホコリ、特定の食べ物などのアレルギー物質、身体的・心理的ストレスなどさまざまです。生活習慣を整え、保湿剤を使用して肌を乾燥から守り、ステロイドなどのかゆみを抑える薬を適切に使用することが大切です。大人になってから、環境の変化やストレス、ホルモンバランスの変化で症状が出る方もいます。当院では、まずは問診でかゆみの症状を伺い、アレルギー検査(採血)でかゆみの原因となる物質を調べます。そのうえで、生活指導や外用薬(塗り薬)、保湿剤、それでもかゆみがおさまらないときは内服も併用します。患者さんの背景(年齢や生活習慣、基礎疾患、お仕事)などにより治療内容は変わります。くりかえす湿疹でお困りの方は、当院までご相談ください。
かぶれ(接触皮膚炎)
かぶれ(接触皮膚炎)は、刺激物やアレルギー物質に接触することで皮膚に炎症が起きる疾患です。原因物質に反応すると、皮膚が赤くなったり、かゆみや腫れ、水ぶくれができたりすることがあります。軽度の場合は、原因物質を避けて、皮膚を清潔に保つことで改善することがありますが、症状が続く場合や悪化する場合は、当院まで早めにご相談ください。
脂漏性皮膚炎
脂漏性皮膚炎は、皮脂が多い頭や顔、耳のまわりにカサカサやかゆみ、赤みが出る疾患です。
赤ちゃんの場合は、生後1年ごろまでに自然に治ることがほとんどです。しかし、思春期以降に起こる場合は、慢性的にくりかえしやすいとされています。皮膚の常在菌の「マラセチア」というカビが関係していると考えられており、ステロイドの塗り薬や抗真菌薬の塗り薬を使用します。また、シャンプーや洗顔など、適切なスキンケアを行い、皮脂が過剰にならないようにすることが大切です。
ニキビ
ニキビは皮脂が過剰に分泌し、毛穴が詰まることで発生します。放置するとへこみや色素沈着などニキビ跡が残ることもあります。悪化する前に早い段階で治療を始めることが大切です。まずは、塗り薬(外用薬)や漢方などでの治療を行いますが、自費によるイオン導入、ケミカルピーリング、ビタミンC外用(化粧水)、ビタミン注射なども行っています。なかなか改善しない方、ある程度治まったけれどニキビ跡が気になる方などお気軽にご相談ください。
また当院のニキビ治療の特徴としては、なかなか治らないニキビに対して婦人科専門医による婦人科診療を行っている強みとしてステップアップ治療として低用量ピル(自費)の内服をご提案する場合もあります。
まずは、ニキビで悩んだやお早目に当院までご相談ください。
蕁麻疹(じんましん)

蕁麻疹は、皮膚に一時的に赤く膨らんだかゆい発疹があらわれる疾患です。通常この発疹は数分から数時間で消えます。原因は、食べ物(卵やナッツなど)、薬剤、暑さ・寒さ、ストレス、虫刺されなどさまざまです。原因がわからない場合もありますが、アレルギー反応が関係している場合が多いです。当院では蕁麻疹の原因物質(花粉、ダニ、ほこり、カビ、動物、食べ物など)のアレルギー検査(採血)ができます。原因を特定し、適切な治療をすることが大切です。
※金属アレルギー検査はできません。パッチテストができる医療機関にご紹介させていただきます。
乾癬(かんせん)
乾癬は、皮膚が赤くなって盛り上がり(紅斑)、銀白色のうろこ状のかさぶた(鱗屑)が厚く付着して、ポロポロとはがれ落ちる(落屑)疾患です。体の同じ部分にくりかえし刺激が加わると出やすく、悪化すると全身に広がることもあります。遺伝的な体質が関係しており、そこに物理的な刺激などが加わると発症すると考えられています。感染症ではないため、人にうつることはありません。まず、ステロイドの塗り薬やビタミンD3の塗り薬を使用します。当院では、乾癬と診断がついている方の継続加療を行っております。乾癬は長期的な治療が必要な疾患です。大学病に通院しているけれど「待ち時間が長い」「遠くて通院に時間がかかる」などでお困りの場合は、当院で大学病院のお薬の処方は可能です。その場合は、大学病院からの紹介状をお持ちください。
ヘルペス
単純ヘルペスウイルスによっておこる感染症で、感染すると発疹や潰瘍(かいよう)ができます。このウイルスは、口唇ヘルペスや顔のヘルペスの原因となる1型と、性器やおしりにできるヘルペスの原因となる2型があります。1型に初めて感染した場合、症状が出ないこともありますが、女性が2型に初めて感染すると、高い熱や激しい痛みといった強い症状が出ることがあります。治療には抗ウイルス薬の飲み薬や塗り薬を使用します。発疹が出る前にピリピリやチクチクなど違和感がある時点で治療を始めると、早く治る可能性が高くなります。気になることがあれば、早めに相談してください。
当院では、ヘルペスを繰り返す患者さんにPIT療法を行っています。PIT療法は「Patient Initiated Therapy」の頭文字をとった略語で、ヘルペスの初期症状がでたら患者さんの判断で薬を服用する治療法です。海外では1day treatmentとして標準的な治療になっています。繰り返すヘルペスでお悩みの方は、当院の皮膚科までご相談ください。
帯状疱疹
帯状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスが原因の感染症です。小さい頃に水ぼうそうにかかると治った後もウイルスが潜んでおり、免疫力が低下すると再活性化して発症します。体の左右どちらか一方に小さな水ぶくれや赤い発疹が生じて帯状に広がり、ズキズキするような痛みが生じます。また、発疹が治った後も長期間にわたって強い痛みが残る(帯状疱疹後神経痛)ことがあります。そのため、水ぼうそうにかかったことがある方は、小さな水ぶくれを見つけたり、痛みが続く場合、できる限り早めに相談してください。
帯状疱疹はこれまでは60代以上の高齢者がかかる病気としてしられていましたが、最近は20代から40代の若い方の帯状疱疹が増えています。水ぼうそうワクチンが子供たちの定期接種となり水ぼうそうの流行が激減し、水ぼうそうのウイルスに接する機会が減ったことも原因ではないかとも言われています。また、コロナ禍もありさまざまなストレスがかかり、免疫が低下したからとも言われています。最初は「痛み」から始まり、後から水疱や発疹がでることが多いので、整形外科を受診して鎮痛剤を処方されたけど治らなく、発見が遅れることも少なくありません。また、若年の帯状疱疹は水疱にならなかったり、わかりにくいこともあります。
『最近忙しい』『ストレスがかかっている』など、免疫が下がっているかもしれない時に、ぶつけたり運動した後でもないのに筋肉痛、腰痛、皮膚がチクチク、ピリピリするなどの症状がでたときは、帯状疱疹の初期症状かもしれません。早めに当院の皮膚科までご相談ください。
当院は、大田区の帯状疱疹ワクチン接種助成事業の協力医療機関です。大田区在住の50歳以上の方は費用の一部を助成されます。ご希望の方はお電話でご予約ください。
水虫
水虫は、白癬菌(はくせんきん)によっておこる感染症です。この菌は爪や足だけでなく、手や顔、頭、陰部など他の皮膚にも感染することがあります。症状に合わせて塗り薬や飲み薬を使います。水虫に手で触れても通常うつる心配はありませんが、手に傷があったり、白癬菌がついたバスマットやスリッパなどを長時間使用したりしていると、感染する可能性が高くなるため、注意が必要です。